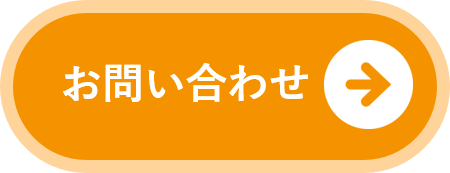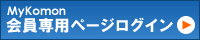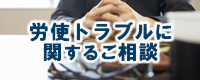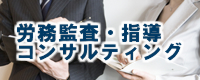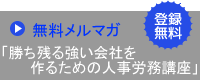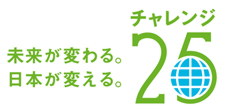就業規則とは
就業規則とは、簡単にいうと「職場全体のルールブック」です。勤務時間や賃金の決定、権利、義務などを詳細に記載し、従業員がこれを守ることで、業務を円滑に遂行できる環境を整える役割を果たしています。就業規則の作り方
就業規則の作成は、以下の手順で進めます。
① 原案の作成
② 過半数労働組合または過半数代表者への意見聴取
③ 過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書の届出
④ 就業規則の周知
また、労働基準法第89条により、就業規則には必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、会社で規定をする場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
必ず記載すべきこと
まずは、どの事業者も必ず盛り込まなくてはならない項目についてです。「絶対的必要記載事項」と呼ばれており、労働時間、賃金、退職に関する内容になります。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
各事業者は、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)の範囲内で、所定労働時間を定めることができます。就業規則には、始業時刻と終業時刻、休憩時間を明記する必要があります。フレックスタイムなどを導入している場合は、その内容や対象者なども詳細に記載していきましょう。
②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の 締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
賃金に関して、基本給や手当などの規定や計算方法、支払方法、支払日などを明記する必要があります。また昇給の時期や、昇給方法なども記載しなければなりません。賃金に関しては記載しなければならない項目が多いかつ、従業員の関心が高い項目になるので、より丁寧に記載した方が良いでしょう。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職には、定年退職や雇用期間の満了、自己都合、休職期間満了など多くのケースがあります。さらに、従業員の自己都合であれば退職を申し出る時期なども記載が必要になります。また、解雇についても従業員が納得できるように、きちんと示しておくことが大切です。
社内制度によっては記載しなければいけないこと
一方、会社の制度によっては就業規則に書く必要がある「相対的必要記載事項」を紹介します。
①安全衛生に関する事項
災害発生時の対応や、定期健康診断、受動喫煙防止などの労働安全衛生に関する事項も、事業所によっては盛り込む必要があります。
②災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
業務災害によって従業員が傷病などをした際には、使用者は補償をしなければなりません。その内容、補償する期間なども定めておくことが大切です。
③表彰、制裁に関する事項
表彰制度は就業規則への記載も、実施すること自体も、義務づけられているものではありませんが、多くの企業が顕著な業績を上げた従業員を表彰しています。
独自の表彰制度を設けて周知することは、従業員のモチベーションアップ向上が見込めます。
まとめ
就業規則をしっかり作りこむことで、従業員の欠勤や退勤、有給取得や、懲戒処分など企業と従業員との間で発生し得るトラブルを防ぐことが出来ます。
さらに就業規則がないと、助成金を申請できない可能性もあります。例えば、キャリアアップ助成金や、働き方改革推進支援助成金などです。
このような助成金は、就業規則の作成や、助成金の要件にあった就業規則の整備が必須です。
就業規則を1人で全て作成するとなると、時間と手間がかかり、抜け漏れも多くなるでしょう。不安な方は社会保険労務士法人Next Partnersにお任せください。
お客様が本業に集中できるように、抜け漏れのない正しい就業規則を、最後まで丁寧に作成いたします。
初めて作成する方も、整備をご希望の方も、お気軽にご相談ください。
立川で社労士(社会保険労務士)をお探しの方は、社会保険労務士法人Next Partnersにお任せください!